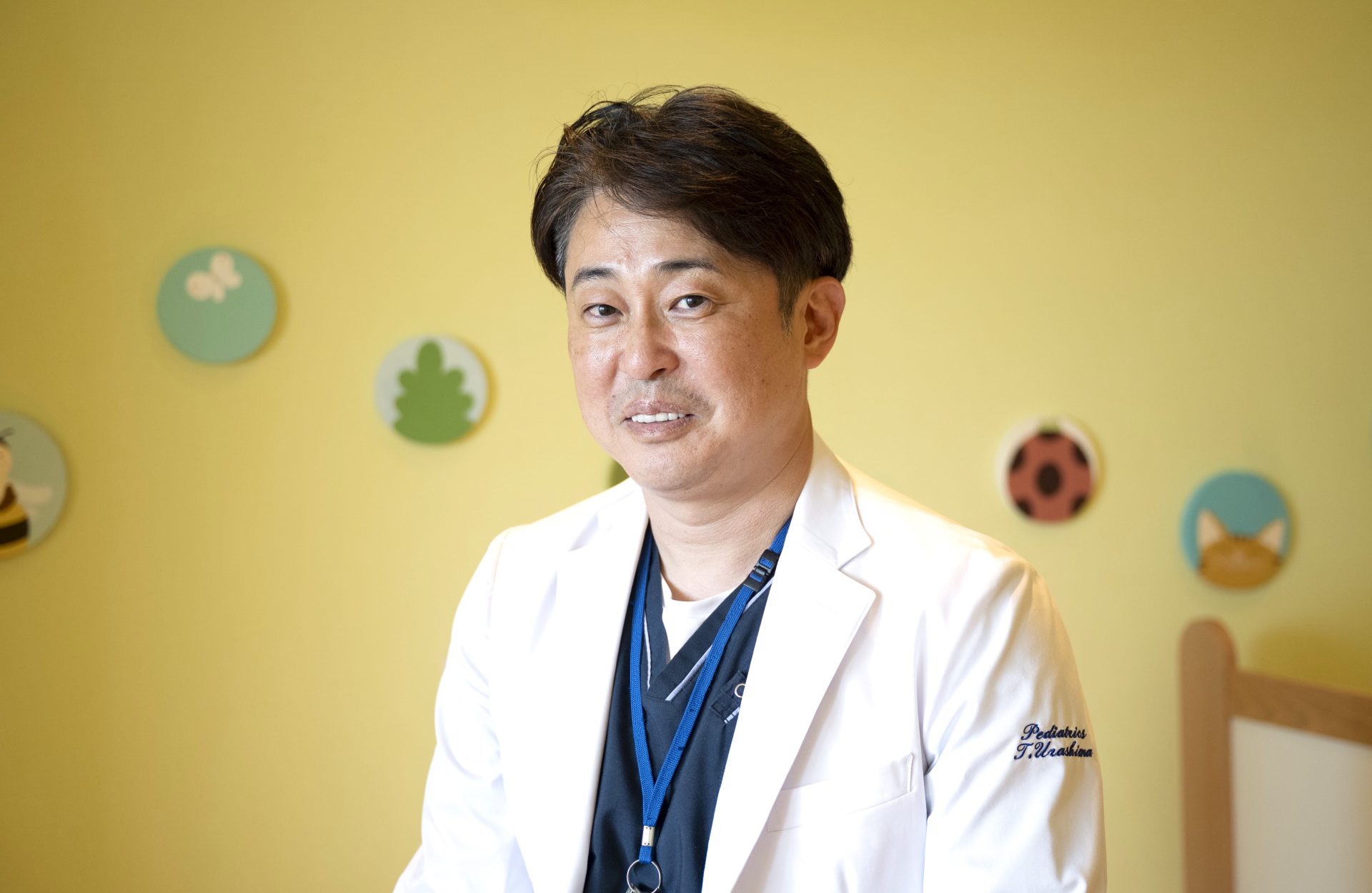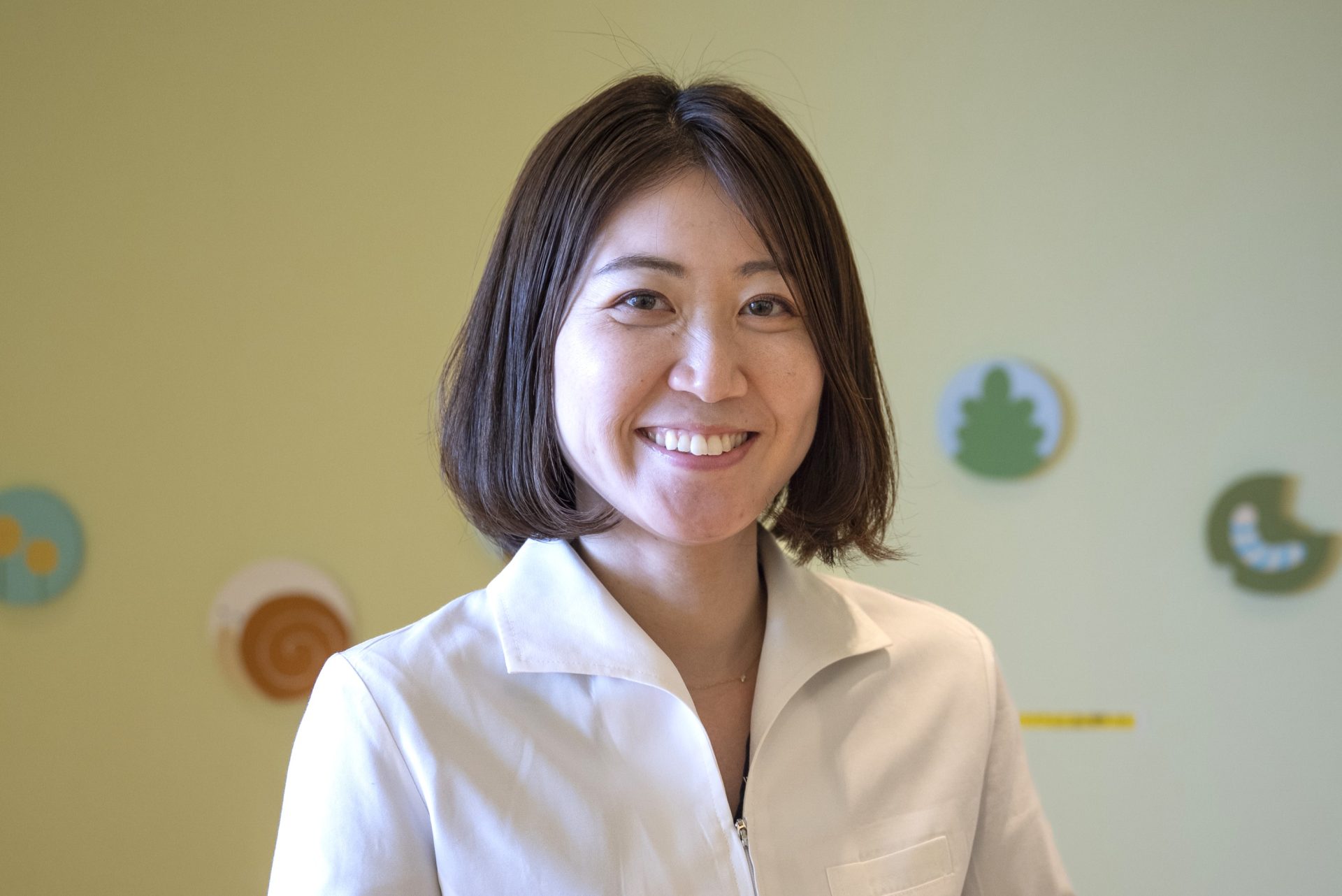小児科
- 小児科について 小児科について
- 診療内容 診療内容
- 医師のご紹介 医師のご紹介
急な疾患から
乳幼児の健診まで
幅広く診療

小児科では、発熱、風邪、頭痛、鼻水、のどの痛み、咳、下痢・嘔吐、腹痛、ひきつけなどの一般診療から、乳幼児健診・予防接種・育児相談・在宅医療支援、入院加療まで行っています。必要に応じて大学病院・小児病院や地域の医療機関と連携し、お子さまに最適な医療を提供しています。また、愛育クリニックとは電子カルテを共有し綿密な連携を行っています。
-
小児科外来
主に下記の症状に関して診療を行っています。
必要に応じて当院専門外来、高度機能病院へご紹介いたします。
◎発熱 ◎咳/気管支喘息 ◎下痢/嘔吐 ◎便秘 ◎感染症(インフルエンザ、アデノウイルス、RSウイルス、ヒトメタニューモウイルス、溶連菌など) ◎熱性けいれん ◎血便 ◎急性中耳炎 ◎鼻づまり/副鼻腔炎 ◎クループ ◎頚部リンパ節腫脹 ◎あせも ◎乳児湿疹 ◎乳児脂漏性皮膚炎 ◎皮脂欠乏症 ◎おむつかぶれ ◎とびひ ◎アトピー性皮膚炎 ◎伝染性軟属腫(水いぼ) ◎いちご状血管腫 ◎皮膚のかゆみ ◎あざ(母斑) ◎夜尿症 ◎尿路感染症 ◎血尿/蛋白尿 ◎亀頭包皮炎など

-
小児科入院
小児科病棟として4床室×3室、2床室×1室、個室×8室の用意がございます。病棟には保育士、薬剤師が常勤しており、プレールームも完備しています。
*料金は4床室・2床室が6,000円/日、個室は10,000~30,000円/日
*4床室は完全看護(面会時間12時~20時)
*乳幼児の個室利用は原則として養育者の付き添いが必要
*レスパイト入院の受け入れを行っています(医療ケアを要するお子さん対象)当院地域医療連携室(03-6453-7300<病院代表番号>)へお問い合わせください

-
小児科診療体制
小児科は24時間・365日の小児救急医療を継続するために、複数主治医制で入院患者さんの診療を行っています。毎日チームカンファレンスを行い、診療経過を共有し、適切な治療を継続します。

-
感染症精査
感染症状によって下記の精査を実施しています。
・迅速検査(インフルエンザ、RS、ヒトメタニューモウイルス、溶連菌、アデノウイルス、新型コロナウイルス、マイコプラズマと含むフィルムアレイを用いた網羅的PCR検査)
・細菌培養検査(院内で実施)
・画像診断(レントゲン、エコー、MRI、CT、造影検査)

-
循環器・消化器・泌尿器疾患の精査(平日9-16時 要予約)
非侵襲的に下記の検査を実施しています。
・心エコー心電図(心雑音、先天性心疾患の精査)
・造影検査(膀胱尿管逆流症、消化管異常の精査)
・腹部エコー(消化器疾患、虫垂炎の精査)
・体表エコー(リンパ節腫脹などの精査)

-
乳幼児健診
赤ちゃんの成長や健康を確認するために、自治体ごとに行われる健診です。お母さんやお父さんから育児のご相談も承ります。平日月曜から金曜日に実施しており、予防接種と同時に受診いただけます。
・公費健診 ※区発行の健診票をご持参ください
(3~4か月健診 / 6~7か月健診 / 9~10か月健診 / 1歳6か月健診)
・自費健診 ※8,000円~
(1か月健診 / 1才健診 / 就学前健診 / 受験用健診など)

-
予防接種
当院では下記の予防接種を行っています。接種をご希望の方は、事前に診療予約アプリ「アットリンク」にてご予約ください。
◎ヒブ(インフルエンザ菌B型) ◎肺炎球菌 ◎ロタウイルス ◎B型肝炎 ◎4種混合ワクチン ◎5種混合ワクチン ◎BCG ◎麻しん/風しん ◎水痘 ◎子宮頚がん ◎日本脳炎 ◎2種混合ワクチン ◎任意接種 ◎おたふくかぜ(流行性耳下腺炎/ムンプス) ◎3種混合ワクチン ◎髄膜炎菌 ◎インフルエンザ(期間限定)

-
専門外来
専門外来では、以下の専門的な診療を行っています。
※初診の場合、まずは小児科外来をご受診ください。
◎小児心疾患外来(川崎病、心室中隔欠損、心房中隔欠損などの先天性心疾患) ◎アレルギー外来(気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギーなど) ◎内分泌外来(低身長、思春期早発症、矮小陰茎、甲状腺機能異常など) ◎神経外来(てんかん、発達障害など) ◎小児外科外来(包茎、水腎症、鼠径ヘルニア、便秘、停留精巣、移動精巣、臍ヘルニアなど) ◎小児形成外科外来(口唇口蓋裂、扁平母斑、血管腫、耳瘻孔、眼瞼下垂、耳介形成異常、折れ耳など先天性形態異常)

-
頭のかたち外来
当院ではジャパン・メディカル・カンパニー社のクルムフィットを採用しています。個々の頭の形に対してオーダーメイドで作成したヘルメットを作成します。
◎費用
583,000円(税込)+別途メンテナンス料(1回3,300円/税込)

-
リハビリテーション
専属理学療法士、作業療法士によるリハビリテーションや装具作成を行っています。※小児科外来を受診して適応をご相談ください。医師の診察後、必要に応じて機能回復・促進のためのリハビリを行います。

-
心理評価・カウンセリング
認定臨床心理士による発達検査、自閉スペクトラム症、知的障害、注意欠陥多動障害、不登校児などのカウンセリングを行っています。※小児科外来を受診して適応をご相談ください。医師の診察後、必要に応じて検査やカウンセリングを実施します。

-
副院長 小児科部長 浦島 崇

- モットー
- 「一期一会の診療」
- 専門分野
- 日本小児科学会認定小児科専門医
日本循環器学会認定循環器専門医
日本スポーツ協会公認スポーツドクター
日本抗加齢医学会抗加齢医学専門医
呼吸機能障害診断指定医
心臓機能障害診断指定医
日本小児科医会子どもの心相談医
出生前コンサルト小児科医
港区小児慢性特定疾患審査委員長

-
医師 田原 麻由

- モットー
- 「子どもを診る、家族を診る、
地域を診る」
- 専門分野
- 日本小児科学会認定小児科専門医
日本抗加齢医学会抗加齢医学専門医
出生前コンサルト小児科医

-
医師 梅田 千里
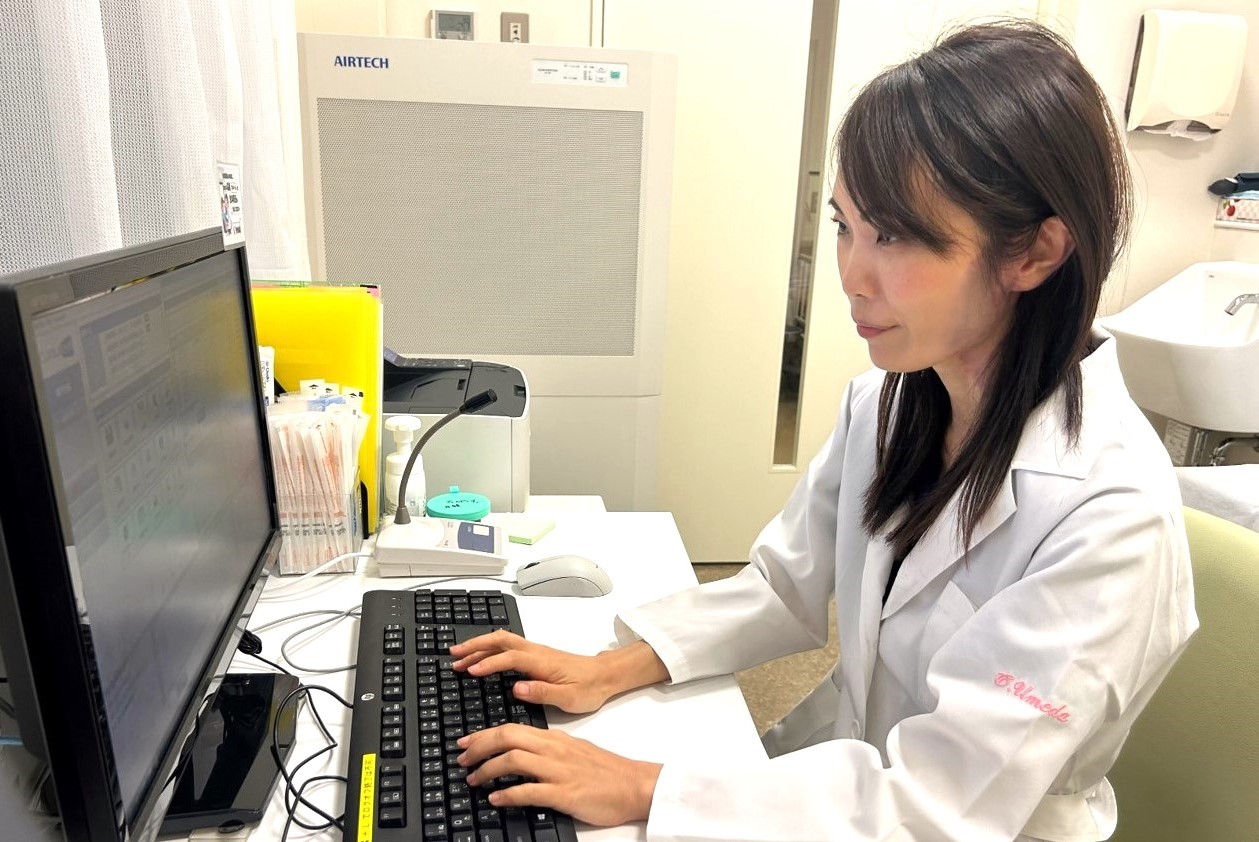
- モットー
- 「誠実であること」
- 専門分野
- 日本小児科学会認定小児科専門医
日本腎臓学会専門医
出生前コンサルト小児科医
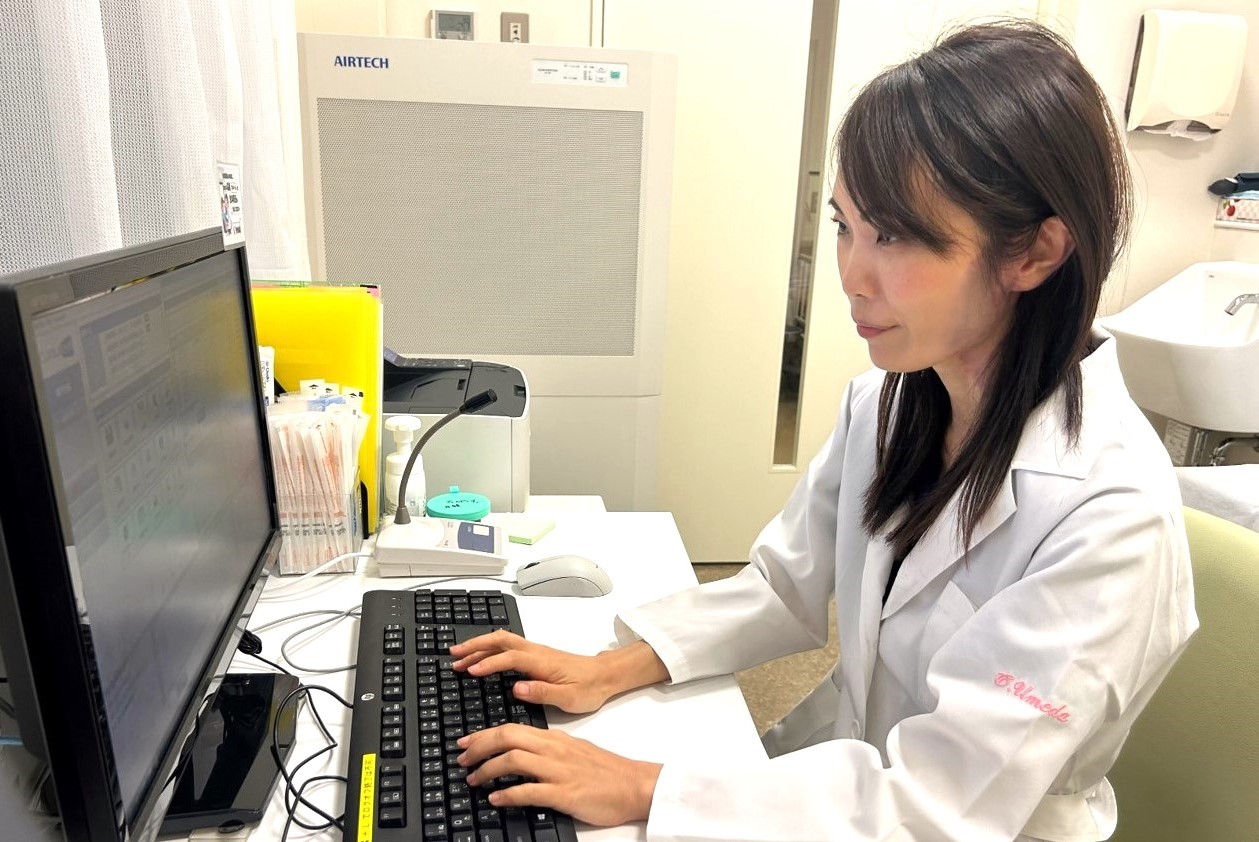
-
医師 沼田 遙
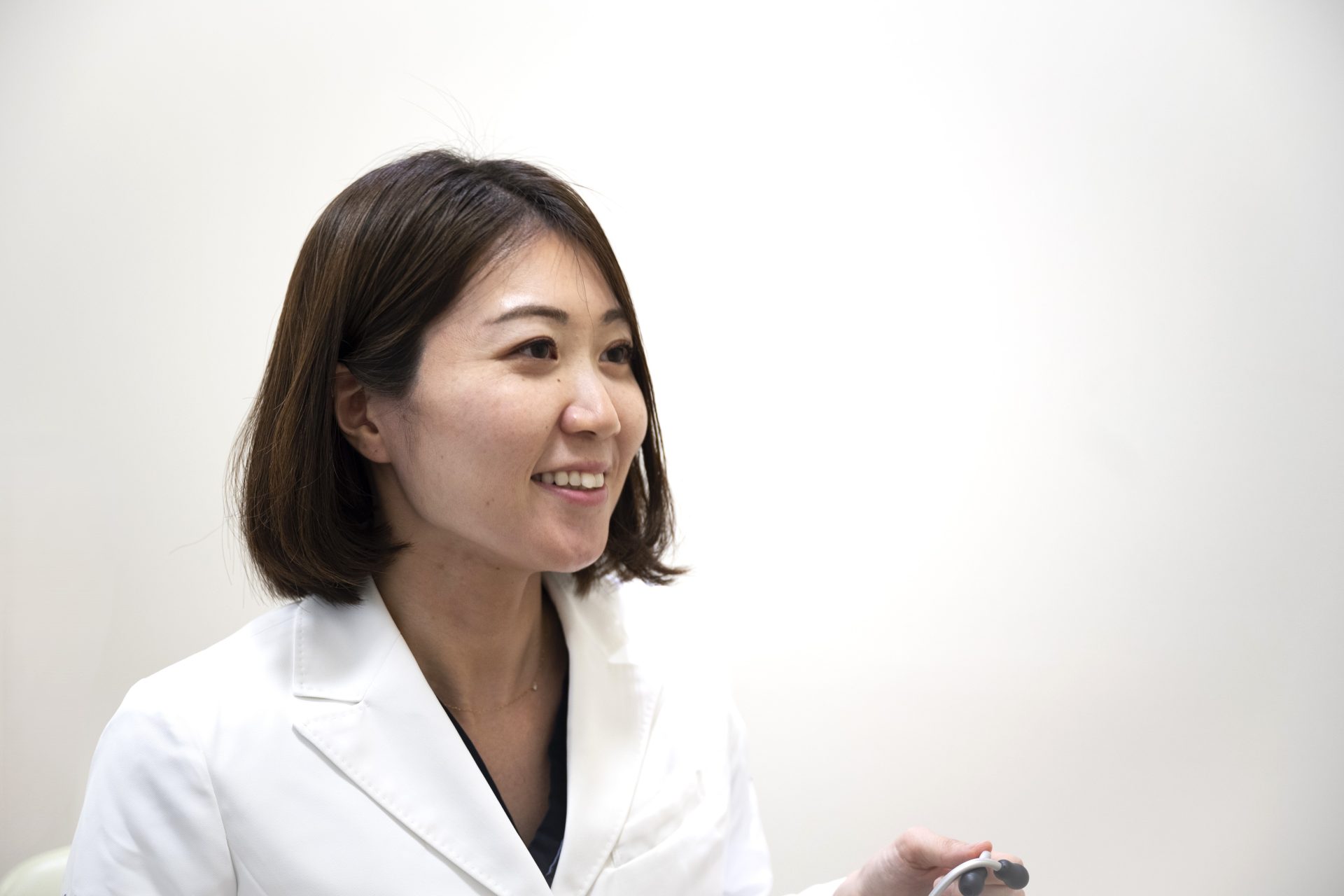
- モットー
- 「安心かつ信頼のおける医療の提供」
- 専門分野
- 日本小児科学会認定小児科専門医
日本内分泌学会所属
日本抗加齢医学会抗加齢医学専門医
出生前コンサルト小児科医
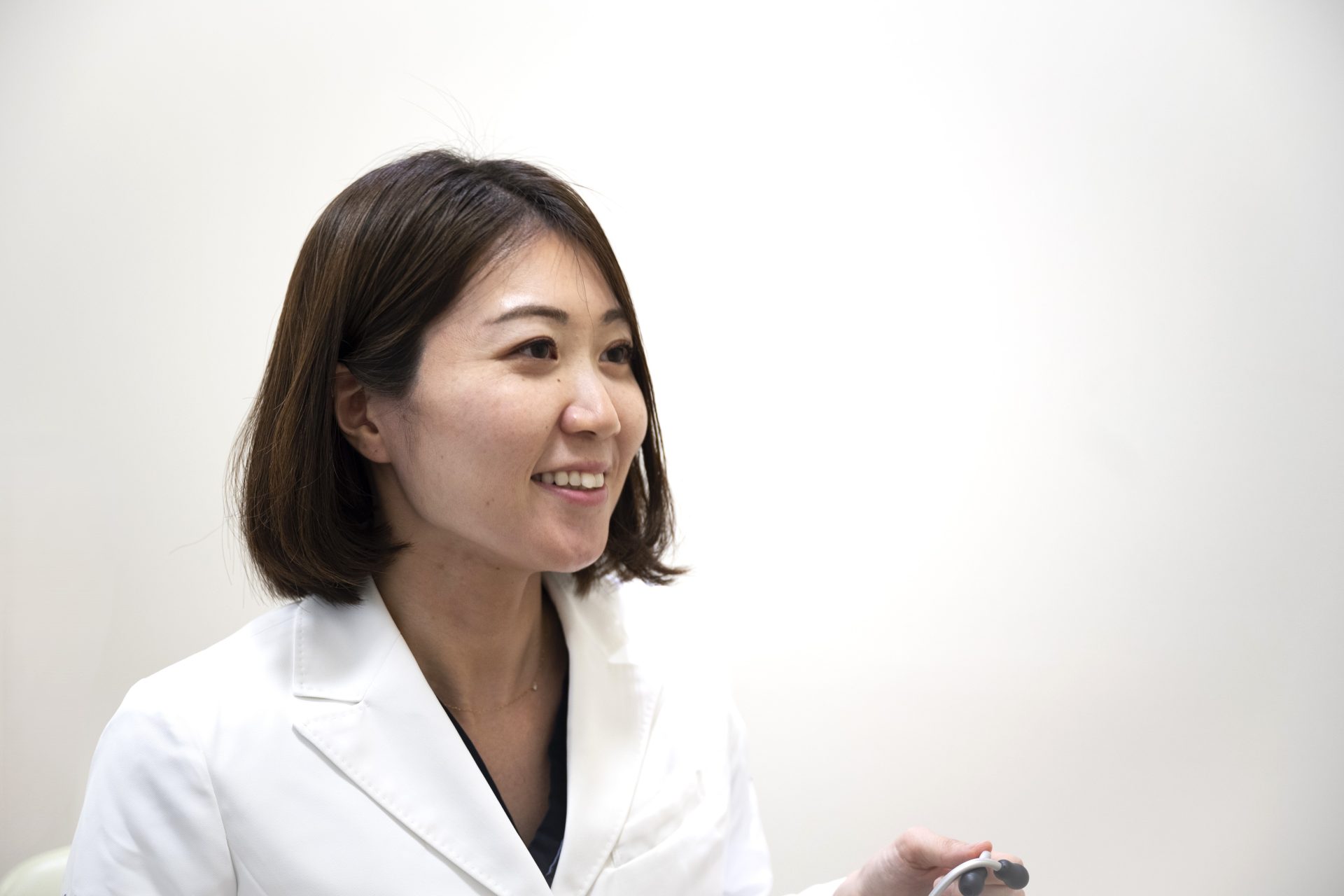
-
医師 山岸 賢也

- モットー
- 「誠心誠意」
- 専門分野
- 日本小児科学会専門医プログラム専攻医

-
医師 新村 南

- モットー
- 「寄り添う医療」
- 専門分野
- 日本小児科学会専門医プログラム専攻医

-
医師 小西 愛里
- モットー
- 「謙虚であること」
- 専門分野
- 日本小児科学会専門医
日本アレルギー学会専門医
-
医師 徳永 愛
- モットー
- 「安心して帰れる診察室」
- 専門分野
- 日本小児科学会専門医
-
新生児科部長(兼務) 松井 美優
-
新生児科医員 (兼務) 水谷 真一郎
-
総合母子保健センター母子愛育会顧問
慈恵大学理事(非常勤) 井田 博幸 -
愛育クリニック 医師(非常勤) 渋谷 紀子
-
愛育クリニック 医師(非常勤) 佐藤 詩子
-
愛育研究所 医師(非常勤) 伊藤 康
-
医師(非常勤) 西川 円佳
-
医師(非常勤) 石井 のぞみ
-
医師(非常勤) 角皆 季樹
-
医師(非常勤) 徳永 愛
-
医師(非常勤) 西村 怜司
-
医師(非常勤) 内田 豪気
-
医師(非常勤) 宮國 憲昭